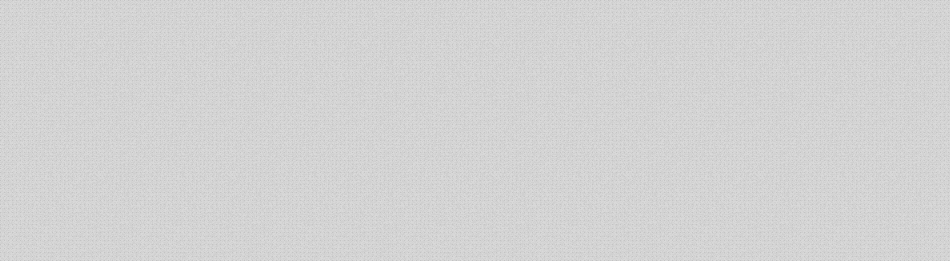文章作品
秋空の約束(冒頭)
父は星座管理人だった。
星座の形は、世界各地の支部責任者が集まって年毎に決める。それには関係しない下っ端。父は現場の人間だった。
小学校の社会見学。南東支部の投射盤に星を配置する父は、とても誇らしそうだった。星の配置は重要だから、やってみたいとせがむ子供に体験させるわけにはいかないのだが、おどけて断る姿は、自分の大事な仕事を横取りされぬよう張り合う子供のようにも見えた。
それが、もう十年も前になる。
今年の春先、父は星になってしまった。いや、それだと移動してしまうんだけれども。とにかく本人のような暖かい日、父は逝った。
薄手のストールを巻き付けて、俺は自転車に跨った。ペダルを漕げば、すぐに坂道を滑り始める。ここをずっと降り、海沿いの町の中央を通過してもう一度登れば、星座管理協会南東支部に到着する。自宅とは同じような海抜なので、坂を下りるまでは常に見えている。高く晴れた青空と薄く引かれた雲を背景に、ドーム状の建物にはラッパ型の星座投射装置が付いていた。いつ見てもこの形は奇妙だ。それが、傾斜で視界から掻き消えた。
ストールを乗せた風はやや肌寒いが、今日は見事な秋晴れだ。まるで春を思わせるような陽光の質に、俺は一瞬眠気を覚えて――
「――っ!」
ブレーキを忘れた。
嫌な摩擦音と焦げ臭さが鼻につく。飛び出してきた子供を辛うじて避け、そのまま自転車で転げ落ちた。俺は景気良くひっくり返り、子供は盛大に肩掛け鞄をぶちまける。
「いっつ……」
うなじをさすりながら地面に手をつき、何とか半身を起こした。関節はじんと痛むが、ジャンパーのおかげで大した怪我は無いようだ。自転車の籠は……いつからへこんでいたか解らない。それよりも、と気になって、俺は子供に駆け寄った。
「大丈夫か? 痛いとことか――」
「どうしてくれるのよぉ!」
が。屈みこんだ瞬間、凄まじい罵声に面食らう。それはキャスケット帽の少女だった。真っ直ぐの髪は長く、今時のお姉さんと差程変わらないワンピースとブーツを身に着けている。子供服はここまで進化しているのかと感心していると、激怒する彼女は唐突に薄いプラスチック板を突き出した。
「割れちゃったじゃない! ほら!」
それは両手を合わせた大きさをした、漆黒の円盤。一枚一枚違う場所に、凄まじく小さい穴を数多開けた三層で出来ており、投射装置に掛ければ別々に回転する。それで等星の段階付けや瞬きを調整し――
「って、投射盤!」
「遅い!」
二層目が真っ二つになっているが、紛れもない投射盤である。この円盤が星座の図面を担っているのだ。と、そこまで考えて、ざっと青褪める。今日は月の変わり目。もしや俺は、今晩から映すであろうこの図面をぶち壊しにしてしまったのだろうか。
「今日だけだったのに!」
「え、今日? 一日限定?」
思わず問い返す。すると彼女は、ぱたりと口を閉じて気まずそうに目を逸らした。するすると視線をずらした先に、この辺りでは馴染みの横綱ゴウリュウを見つけたのか、「あ、猫ー」とわざとらしく呟く。
……よくよく考えれば、正規の投射盤をこんな子供が持ってるはずがない。あの温厚な父親でさえ、見るだけならともかく、触らせてもくれなかったのだ。
「あのう、ちょっとそこのお嬢さん?」
少女の肩がぴくりと動き、活路を探るような半笑いのまま振り返った。地面に二人して座り込んだまま、じりじりと視線で探り合う。
「……ちょっとコレについて吐いちゃみませんかね。実は俺、関係者の息子なんだけど」
すると彼女はにやりと笑んだ。それだけでクロなのだが、無邪気にも思い切り挙手する。
「私も! エジマです!」
「エジマは俺。」
静かに嗤うと、少女はそのまま凍りついた。思わず、こめかみに僅かな頭痛を感じて苦笑う。……きっとあの投射盤は父の作だ。父が生前、約束でもしたのだろう。だが、業務だけには厳格だったはずだけど……?
「ええと、ええとですね、エジマさんが今日それを映してくれるって……」
しどろもどろになりながら、今や俺に確保された投射盤へ目を向ける。「残念だけど」、そう呟いて、俺は投射盤を返却した。
「父は今年の春先に亡くなりまして」
「えっ」
彼女は言葉を失う。子供のこういう顔は酷だ。俺は小さく苦笑した。
「だから何か約束してても、ちょっと果たせない。御免な」
すると彼女は小さく頷いて、そろそろと立ち上がる――はずだったのに。彼女はその予想を見事に裏切って、少女らしからぬ凄まじい力で俺の両肩を掴み肉迫する。
「じゃああんた手伝って」
何を。聞こうとして、咄嗟に口を噤んだ。彼女の目的は、明らか過ぎるほど明らかだ。あの割れた円盤を、現場の皆様の隙を窺って台に設置して投射する。彼女は言外に、二層目を壊した責任を取れと脅迫していた。
「関係者だったなら、何とかなるでしょ?」
「いや、関係者の関係者なんだけど……!」
「ねぇ、十分で良いんだから、お願い!」
断れば呪われそうな勢いで、彼女は俺を拝む。……とはいえ、この仕事の重要さは身に染みている。精確な仕事をしなければ南東支部の面目を潰すことになるし、何よりも……キザキさんが怖い。父の長い友人だが、子供の頃よく怒られた記憶は健在だ。
「……そもそも、何のために?」
困り果てて、俺は投射盤を眺める。光の強弱を現す三層が同時に空へ映されて初めて、図案が判明するのだ。現段階では何の形かさっぱり解らない。
「……今日で、時効なの」
もごもごと、彼女は呟いた。目を向けるが、俯いたせいで表情はよく見えない。
「今日いっぱいでお父さんが帰らなかったら、死んだことになっちゃうの」
もしかしたら、父の約束は最後の砦だったのかもしれない。失踪中という意味か俺は尋ねたが、彼女は首を振る。長い髪がさらさらと揺れた。
「去年海難で船が沈んだから……今年で」
「……それで、これには何が?」
もしや、連絡先が記されているのでは。けど、生きていれば連絡は来るはずだ。まさか住所を忘れてはいないだろうし、そういう状況で連絡先を夜空に投射しても、自宅とは認識できない。だから無駄だとそう思っていたのだが、彼女は再度首を振った。そして何も言わずに、じっと俺を見上げる……かと思うと、勢い良く俺の腕を引っ張り上げた。
「だからね、秋の日は釣瓶落とし。急ぐ!」
俺のささやかな拒否は完全に退けられる。彼女はちょこまかと動き、いつの間にか自転車を起こしていた。やれやれとサドルに跨り、ふと思い出して振り向いた。
「ところでお嬢さんのお名前は?」
彼女は車輪の軸に両足を、俺の両肩に手を掛けて、不敵に笑う。
「ハルミ。出発だ、エジマ隊員!」
……当然のように、部下に任命されていた。
フィンランディア(抜粋)
小さな屋敷には、通いの家政婦しかいなかった。
私達が訪れたときも、到着したばかりの老婆が門扉の鍵を開けようとするところだった。
彼が亡くなって数日。遺体はアパルトマンを別に借りていた母親の手を離れ、エーメ伯爵の元にある。その報告と共に、私達は彼女から遺品の譲渡を依頼された。幸いなことか――哀れなことか。あんなにも愛情に飢えていた青年の願いは、遂に叶えられなかったと痛切に知らされる。イレールが唇を読んだその通りに。
一階は居間と台所と使用人部屋であり、二階全てを私室にしていたようだ。軋む階段を昇りきり、長身の青年には窮屈だったろう、小さな扉を開ける。しかし現れたのは、それも使用人部屋かと思うほど手狭な寝室だった。
綻びた敷物に、簡素な寝台。象牙色のカーテンは清潔だが古く、机に並べられた書物の数々だけが、辛うじて住人は若人であると告げている。学びかけのラテン語、読み込まれた聖書、彼の愛した美術史に、共和の思想。積もり始めた埃に指を滑らせて、イレールは金の箔押しを辿った。碧眼は、何も語らない。
部屋は奥にも続いているようだ。机の引き出しから鍵を探し出し、小さな戸を開ける。ぼんやりと煤けた金色のノブを捻ると、中からはつんと油彩の匂いが漂ってきた。
自然と、足音を忍ばせる。冷えた空気に背筋が伸びる。油絵具だけではない、木の、紙の、黒炭の匂いがそこには充満しており、奇妙に絡んで満ちていた。部外者は容易に関わることの出来ぬ、動いただけで壊れてしまうのではないかと反射的に身構える空気。つまりそこは、残りの部屋全てを貫いて造った、彼のアトリエ。
先に進んだイレールがひたりと足を止める。
目線の先にあるものを見定めようと、後を追う。そうして、愕然と立ち尽くした。
厚いモスグリーンのカーテンに閉ざされた室内には、描き潰されたスケッチブック。散乱するクロッキー帳。描きかけの紙、紙、紙。張り終えたキャンバスが幾つも重ねられ、あちこちに置かれ、複数の画架(イーゼル)にも残されていた。
その全てが。
「フィンランディア……!」
イレールが、彼女の名を呻く。小さな後頭部だけでも、立ち上る怒気は容易に確認できた。
微笑む女、扇情的に視線を流す女、少女のように笑う女、慈しみを浮かべる女、ふと目を伏せたときの女、彼女の様々な表情が、そこには描写(スケッチ)されていた。無数に散らばった、紙の全てに。
彼はいつから描いていたのだろう。イレールがあの屋敷を訪れたときは、最早手遅れだったのか。あれほど慕っていたエドアールドの死さえ覆い隠すほど、彼女の存在は強烈だったとでもいうのか。
「イレール、」
だから私は、小さな肩へ手を添えて、噛み締めるように口を開いた。
「復讐のためではない、更なる犠牲を出さぬためだ」
だから彼も、敢えて二の句を継いだ。
「解っているよ、ハインリヒ。でも僕は、ベルザーリオを奪われた」
私達は視線を交わさない。私は部屋の全てを、彼は描き散らされた全てを目に焼き付けるようにして、ただ、言葉のみを交わす。震える声は怒りに凍え、最早我々は後戻り出来ぬのだと告げた。
「僕がどんな人間だか、君は知っているだろう?」
そうして彼の碧眼は振り返り――
* * *
モンマルトル通りをひたすら北上する。先の改革により、新たに市街へ迎え入れられた新興区画。建設中の白い寺院を北東へ頂く丘。それを目指すように、キャブリオレの辻馬車で小路へ入っていく。冷えも漸く和らぎ始め、外気に晒される幌馬車でも苦にはならない。夜闇の中、石畳を闊歩する蹄の音はどこか澄んで耳に馴染む。
つい先程まで絢爛な広間にいたというのに、重い車輪の音が響く、嘘のように静謐な夜更けである。激しい情熱と憎悪の歌劇に別れを告げ、イレールとベルザーリオには早めの帰宅を言いつけて、オペラ・ガルニエを後にした。
あの、フィンランディアを伴ったエドアールドの瞳。思い出すと、気が沈む。彼の清廉さは好ましいが、その切っ先はいずれ自身をも抉るだろう。可哀想に、ベルザーリオが怯えるほど危惧するのも無理はない。
隣席の御者が少し手前に停めたせいで、ガス灯で照らされる店の盛況ぶりがよく窺えた。引っ切り無しに詰めかける紳士淑女、もしくはそれに準ずる人々。歩み寄る毎に、盛大な笑い声やけたたましい嬌声が強くなる。
苦笑を浮かべ、私も山高帽を被り直した。扉は店の男が開けてくれる。看板には、
「黒猫(シャ・ノワール)」。
「今日は演ってるよ、幸運だね、アンリ」
薄く笑んで礼を述べると、彼は奥を示した。喧騒はいつの間にか止み、潜めた声の向こうから、心洗われる旋律が室内を満たしている。荘厳たるピアノと、共に彩る麗しきソプラノ。ガス灯の光量が偏っているせいか、充満する紫煙のせいか、店内は薄暗い。いや、突き当たりへ設えたスクリーンに、影絵が映されているからだ。
歓談する人込みをすり抜けながら、中ほどの席へ進む。教会さながらに配置された三人掛のベンチ、その左翼の通路脇に腰を下ろす。正面では黒猫を描いた額縁がスクリーンを囲み、映される背景は色を変え、柔らかな灰青で夜を染めていく。投影されるシルエットは、海面へ浮かぶ小舟の群れ。筆致は船体の木目まで写し取ったかのように細やかで、小さな灯りが、波間に反射する幻想的な趣を蘇らせる。
さて、今宵はどの場面からだろうか。ふくよかな高音は、厳かに、だが優しく神の子の旅路を歌い上げた。
「アンリ、いらしてたのね」
流行りのルーマニアワインを片手に、顔見知りの女給が現れる。グラスと同じ艶やかな紅色の唇で、やや俗っぽく微笑んだ。客層のせいだろうか、袖無しのドレスからは僅かに絵具の匂いが感じられる。代金と引き換えに彼女からグラスを受け取り、私は帽子を取った。
「良い夜ですね、マダム。今日も盛況だ」
「出し物のおかげよね。ここは、若いけど芸術家の子が多いでしょう? こんな演目がうけるなんてねぇ」
帽子を被り直す向こうで、スクリーンは刻々と情景を変えていく。月明かりが皓皓と照らす、静かな夜。伸びやかなソプラノは私を陶酔へ導き、許されるものであれば永久に浸っていたい。けれども、続く言葉が私を連れ戻す。
「でも話題は『フィンランディア』でもちきりよ。また新しい紳士が名乗りを上げたんですってね」
「……朝刊を御覧にでも?」
意図せず、声が低くなった。先の観劇での邂逅を思い出す。エドアールドが名乗りを上げたことは、既に報道されている。上演中のためと捉えたものか、彼女も私を真似て囁いた。
「そうね、それから昨日の夜会にいたって人からも。賭けようとするけど――また成立しやしないわ」
エドアールド=アンリ・ド・エーメ。エーメ伯爵家嫡男。高潔な姿勢と、地位ある者の誇り、鋭い眼差しを持つ理知的な青年。親しくしていたジェルマン・ベールを殺されて、遂には耐えきれず、フィンランディアに接触を図る。世評とは概ね一致しているだろう。彼は裏表があるような人間では無い。その清廉たる様は、時に危うさを孕む。
「お隣、失礼致します」
不意に左隣へ、キャスケット帽を目深に被った男が腰を下ろす。気を利かせた彼女が画家連中の元へ席を外したのを確認すると、私は彼に発言を許した。
「『一人目』の確認が取れました。南部出身、豪農の嫡男だったようです」
――そもそもこの連鎖は何が始まりだったのか。
フィンランディアの決闘は、何をきっかけにしてここまで広がっていったのか。これ以上の被害者を出さないためには、未だ名乗りを上げぬ部外者が予め調査する必要がある。当事者になってしまっては冷静でいられない。
調査の方法は至って単純である。関係者を全て遡ればよい。民衆が忘れようとも、遺族は忘れないのだ。一本の糸を丁寧に辿っていけば、いずれは一人目の男に辿り着く。初期の段階では報道もされていなかったため、思うより時間を喰われてしまったが、どうやらやり遂げてくれたようだ。
だが、一人目が貴族でないというのは些か予想外である。
「その男は、弟の件で女に絡んでいたらしいと……下町の店屋連中が覚えていました。田舎での事件がどう、と言っていたようです」
一人目の男が何故決闘にもつれ込んだのか。弟の件とは何であるか。グラスを揺らしながら、私は相槌を返す。視線の先で影絵劇は進行するも、物語や歌声は最早耳に入らない。人々の談笑すら、我々の会話を閉じ込める遮蔽物のように都合が良い。――兎角、動かねばならないだろう。
「解った。私が同行する手配は出来ているね?」
「はい、旦那様。……ただ、少しばかり」
更に声を顰めて、男は口籠る。私はちらと視線だけを向け、許した。
「言ってみなさい」
「その、女はあのように荒れた屋敷に住んでいるにもかかわらず、『一人目』の決闘のときから既に、赤い装束で現れていたようなのです。下町では質素な服装だった、という証言も気掛かりで」
彼の疑念は私の推理を助長した。いや、飛躍と言うべきか。そもそも疑念は当初より付き纏っていたのだ。舞台のような筋書きといい、仕立てられたような生活といい、彼女には共犯者がいるのではないかという疑念である。
私は立ち上がり、彼にグラスを押しつけた。呆然と見上げる面に微笑んで、上着の襟を合わせ直す。
「参考にしよう、それはサービスだ」
画像・映像・その他の作品
作品の登録がありません。